
私はまもなく、78歳になる。その78年の間、純粋に太鼓と寝食を共にしてきたのが58年間。この広い世界にただ一筋の道を歩んできた人々は多々あり、私などはいまだ未熟者に過ぎないが、それでもこの58年間には山あり谷あり。語れば尽きぬ思い出と、決して忘れることのできないたくさんの人々の面影がある。そうした多くのシーンを、これまで折々にこの『昭利の一本道』という一人語りで綴ってきたが、この物語もそろそろおしまいにしようと思う。そこで今回は、私の太鼓人生の「総括」として、あらためて来し方の主なできごとを振り返ってみる。
❖19歳の出会い
太鼓づくりの家に生まれたものの、次男であるがゆえに必ずしも家業を継ぐことを求められていたわけではなかったが、高校時代に福井の太鼓の名手・権兵衛太鼓の故玉村武氏と出会ったことが、私の進路を決めた。玉村氏の薫陶を受け、太鼓の世界への扉が開かれた。
❖1975年 ボストンでの衝撃
24歳の時に『佐渡國鬼太鼓座』初のアメリカ公演に同行してボストンに渡り、太鼓がオーケストラや舞台芸能として新たな歴史を刻む瞬間に立ち会った。この経験は、私の後の活動の原点となった。

「でんさんと最後の仕事」↑
❖林英哲氏との出会い
1984年、『佐渡國鬼太鼓座』座員をへて『鼓童』を退団後、ソロ奏者として活躍されていた林英哲氏と上野の不忍池近くで偶然出会い、翌年、世界で初めて和太鼓でカーネギーホールに出演した英哲氏に同行。この時から、太鼓が持つ可能性をさらに広げたいと強く思った。
❖地域との結びつきと未来へ向けた取り組み
1990年『太鼓の里構想』を掲げ、最新の動力技術を導入した新工場、世界の打楽器を展示した太鼓資料館、宿泊もできる太鼓練習場、空調設備を備えた新倉庫、原木の乾燥研究所を建設。地域とのつながりを深めながら、太鼓の伝統を守りつつ、新たな可能性を模索した。
❖太鼓文化発信の新たなステージ設立と、女性太鼓グループ「炎太鼓」立ち上げ
1986年、金沢のデパートアトリオにアンテナショップを開設し、太鼓を含めた地域文化の発信拠点としての役割を担う。また、女性だけの太鼓グループ『炎太鼓』を立ち上げて一世を風靡した。この挑戦は女性が主体的に太鼓文化に関わる先駆となり、1992年にはロシア赤の広場で開催された山本寛斎氏主催のファッションイベント『ハロー ロシア』に参加。寛斎氏との交流は氏が亡くなる2020年まで続き、長期にわたる国際的な活動の礎となった。


❖太鼓専門情報誌『たいころじい』の発刊
1988年、世界で初めての打楽器専門誌『たいころじい』発刊により、太鼓文化について学術的・哲学的な視点から情報を追求。さらに1995年に文化ゾーンとして多目的ホール『浅野ーEX』をオープンし、新たな文化交流の場を創出した。
❖太鼓コンサート『壱刻壱祭』から『白山国際太鼓エクスタジア』へ
1993年から太鼓の野外公演『壱刻壱響祭』を開催。1997から『白山国際太鼓エクスタジア』と名称を変え、現在も多くのボランティアの方々の協力をいただきながら継続中。




❖プロ太鼓チームの立ち上げへの貢献
1970年代以降、『佐渡國鬼太鼓座』『鼓童』『林英哲』『和太鼓倭』『TAO』『志多ら』『三宅島芸能同志会』など、プロ太鼓チームの立ち上げに深く関わってきた。また、多くのソロ奏者や地域の太鼓チームの発足にも貢献。これまでに1万組を超える太鼓チームの支援を行い、その発展に寄与したと自負している。そうした中で時代の変化を感じつつ、三世代が共存する現在、太鼓文化は大きな変化の波を迎えている。太鼓文化はこれからどう発展していくのか。つねに優秀なスタッフに恵まれ、58年間にわたって「太鼓文化」の隆盛を目の当たりにできたことは、私にとって大きな幸せだった。
❖ものづくりへの取り組み
1.工場の省力化の実現
製造工程の効率化を目指し、以下の機器を開発・導入
- 自動桴製作機(3台):桴(ばち)の生産を効率化し、大量生産を可能に。
- 桶組み立て機:桶胴の組み立てを省力化し、高精度での生産を実現。
- 締太鼓製作機:締太鼓の製作工程を効率化し、品質の安定化を図った。
- 万能中彫機:多用途に対応可能な中彫機で、製作の幅を広げた。
これらの取り組みにより、従来の太鼓製作の伝統を守りながら、生産性と品質の向上を両立させることができた。
2.木工技術向上とデザイン性への挑戦
Ⅰ 革新的な木工技術の開発
生産工程の効率化と品質向上を追求し、以下の革新的な技術を開発・導入した。
- 木工ハイブリッド自動乾燥機(4台):太鼓の原木である木材の含水率を9%まで正確に管理し、品質の安定化を実現。
- 本張り荷圧機:太鼓革の張り工程において、均一かつ高精度な仕上げを可能にした。
Ⅱ グッドデザイン賞への挑戦
2001年から財団法人日本産業デザイン振興会による総合的なデザイン評価制度『グッドデザイン賞』に挑戦。2001年、2002年、2005年、2015年と4度にわたり受賞。日本の伝統的な太鼓の意匠と現代デザインの融合を象徴するできごとだった。
【思い出の写真】

「笹川良一先生と」↑




「はじめての太鼓演奏」↑


これらの挑戦は、伝統を守りつつ新しい価値を生み出す「ものづくり」の象徴であり、感慨深い思い出として心に残っている。こうした取り組みが評価され、2006年に秋篠宮殿下を、2007年に常陸宮殿下ご夫妻をお迎えしたことはこれまでの努力や活動が認められた証と感じ、誇りとともにさらなる前進への大きな励みとなった。
なお、これまで多くの方に支えられて、太鼓文化の貴重なワンシーンに立ち会えた事に感謝もうしあげます。ありがとうございました。
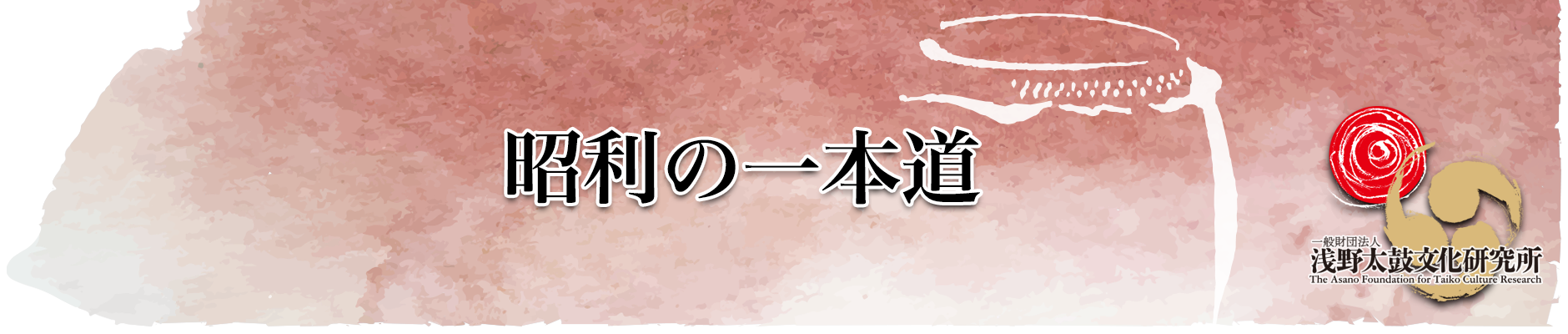
コメント